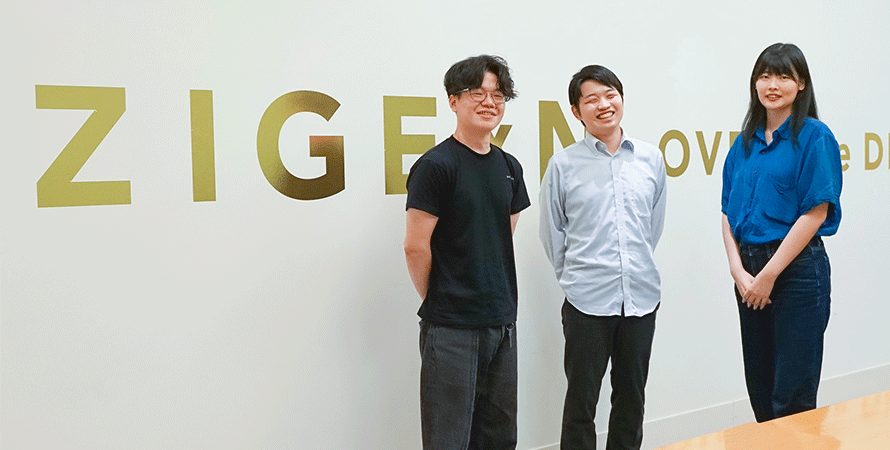「若手が新卒を育てる」カルチャーづくり|じげんネクストリーダープロジェクト3年目の現在地

2023年度の新卒受け入れを機にスタートした、じげんの新卒研修プログラム「ネクストリーダープロジェクト(NLP)」。「若手が新卒を育てる」という新しいアプローチのもと、立ち上げから3年を経た今、社内ではどんな変化が生まれているのか。立ち上げから関わる西尾(17卒)、2年目を担った阿部(20卒)、そして今年度のリーダーを務める青木(22卒)、3名のプロジェクトメンバーに話を聞いた。
目指すのは、「安心して長く働ける」環境づくり
NLPは、もともとどういった目的で始まったプロジェクトなのでしょうか。
西尾:発足当初の目的は、新卒が安心して長く働ける環境をつくることでした。特に23卒は過去最多の入社人数だったため、受け入れ体制や研修内容の見直しが急務でした。
過去の新卒データをすべて洗い出し、これまでのキャリアの傾向や離職の原因などを分析したところ、創業期からの「キャリア設計」「ロールモデル」のアップデートが必要なことに加え、コロナ以降の年次に関しては「同期とのつながり」にも課題が見えてきました。加えて、事業の多角化が進み、組織の数も増えたので、配属先に育成を任せるやり方では限界があると感じていました。
こうした背景を受け、短期的なインプットだけではなく、現場での成長やキャリア形成まで見据えた、会社全体での長期的な支援体制が必要だと考えました。そこで組織横断型プロジェクト「ネクストリーダープロジェクト(NLP)」を立ち上げ、研修プログラムの全面リニューアルを行うことになりました。
もともと2週間だった新卒研修を、3年間のプログラムとして再構築したんですよね。
西尾:はい。最初の1年間はNLPメンバーが中心となってしっかりと並走し、その後の2〜3年目も継続的にフォローしていく──そうした長期的な伴走体制を整えることで、日々の悩みを相談しやすい環境をつくり、キャリア形成を長く支えられる仕組みを目指しました。
ユニークなのは、NLPメンバーをすべて”じげんに新卒入社した若手社員”で構成している、という点ですね。
西尾:そうですね。私は17年、阿部は20年、青木は22年の新卒です。
入社直後に感じる戸惑いや悩みは、少し前に同じ経験をした先輩だからこそ理解できる部分があると思うんです。若手同士が支え合う関係性を築くと同時に、「育てられる側から、育てる側へ」と先輩社員が成長していくきっかけにもなってほしいと考えています。

成長の土台作りから、次のステップへ
NLP2期目では、どのようなことに取り組まれたのでしょうか。
阿部:主に取り組んだのは、1期メンバーが構築した新卒1年目向け研修プログラムのアップデートです。
NLPには、「未来の事業責任者を増やす」という大きなテーマもあります。そのためには、マネジメントを任せられる素養や、事業を多角的に見る視点を育むことが重要です。1期では「安心して成長できる土台をつくる」ことを重視していましたが、2期ではそこに加えて、「事業をつくる経験を早い段階で積んでもらう」「一人ひとりの成長スピードを上げる」といった部分を意識してプログラムを再設計しました。
具体的には、どのようなアップデートを?
阿部:入社から半年後に行う「事業立案研修」の設計を大きく見直しました。この研修では、複数のテーマから選んだ題材に対して事業プランを構築し、役員の前で発表します。1期ではチーム戦でしたが、2期からは個人戦に切り替えました。
この変更には2つの狙いがあります。
ひとつ目は、一人ひとりが事業を一から立ち上げるプロセスを網羅的に体験し、自ら考え抜く力を養うことです。チームで取り組むことで得られる学びもありますが、どうしても役割分担や負担の偏りが出てしまいます。個人で全工程を担うことで、主体性を養い、事業をつくるのに必要な視点をより早期に磨けると考えました。
2つ目は、次期NLPメンバーの育成です。研修参加者にはマネージャー陣が“メンター”(業務の進め方や課題設定のサポート、発表内容へのフィードバックを行う役割)としてつきますが、そこに加えて新卒2〜3年目の若手社員を“バディ”(メンターよりライトな壁打ち相手・相談役)として配置しました。次年度以降のNLPを担う可能性のある人が、「育てる側」として後輩に寄り添い、客観的な視点や、ロジカルに伝える力を身につけることを目的としました。

2期目でやり切れなかったことはありますか。
阿部:はい。「1年目を終えた後に、自分で次のキャリアのステップを選べる仕組み」をつくることです。もちろん与えられた環境で成長することも大切ですが、「もっと挑戦したい」という人に、別の入口や新しいステップを提供できるようにしたかったという思いがあります。
だからこそ3期目NLPでは、青木をはじめとするメンバーに、新卒2〜3年目の成長をどう支援し、どんな枠組みを用意できるかを考えてもらえると嬉しいなと思います。
プロジェクトから会社の文化へ──3年目の現在地
3期目ではどのようなことに取り組みたいと考えていますか。
青木:僕たち22卒が入社した当時は、まだ「どこに課題があるのか」すらわからない状態だったと思います。ですが、NLPが3年続いてきたことで、育成の中でどこに課題が生まれやすいのかが少しずつ明確になってきたと感じています。特に、新卒の1年目にどんなモチベーションの変化があるのか、どこでつまずきやすいのか──そうした分析は、実際に現場で見てきたNLP1・2期の先輩方だからこそ整理できた部分だと思います。
そのうえで3期目の私たちは、先輩方が明らかにしてくれた課題を引き継ぎ、「それをどう具体的なアクションにつなげるか」をテーマに取り組んでいきたいです。
また、これまでの研修が「やって終わり」にならないよう、受講者本人の実感だけでなく、周囲からのフィードバックも含めて成長を可視化できる仕組みづくりも計画しています。研修と評価をセットで設計し、人事評価にも反映できるよう制度面での連携を進めることで、NLPが全社的な育成の仕組みにきちんと組み込まれていくことを目指しています。
3年目を迎え、NLPは社内にどんな変化を与えていると感じますか。
西尾:1期目の私たちは、まずは研修のフレームをつくることで精一杯でした。それが2期・3期と引き継がれ、さらに発展している姿を見ると、本当に頼もしいし、やってよかったなと思えます。 「若手が新卒を育てる」という仕組みがこうして3年かけて形になり、定着率の向上といった形で成果が出てきているのは、本当にうれしいですね。
青木:僕自身、22卒としてNLPに関わる中で一番感じているのは「縦のつながり」が強まったことです。これまでは同期同士の横の関係はあっても、世代をまたいだつながりは今よりも弱かったように思います。NLPを通じて先輩が後輩を自然に気にかけるようになったり、世代を超えたネットワークが少しずつ広がっています。研修の仕組みがあるだけでなく、こうしたカルチャーが芽生えてきたのが3年目の大きな変化だと思います。

阿部:私は、組織の強さはカルチャーの強さに比例すると思っています。NLPはまさにそのカルチャーをつくっていく取り組みです。
自分たちの代で経験したことを次の代にどうつなげるかを考える──その積み重ねが、全社のエンゲージ向上につながりますし、新卒にとってもかけがえのない経験になると思います。
NLPはプロジェクトや仕組みそのものよりも、「育成は誰か一人の役割ではなく、みんなでやるもの」という意識を根づかせることが一番の目的だと感じています。若手のうちから“誰かを育てる側”に立つ経験ができるのは貴重ですし、そのサイクルが世代を超えて続いていけば、じげん全体のカルチャーとして力強く残っていくと信じています。
西尾:NLPという横断組織があることで、組織課題に取り組み、新しいプロジェクトや仕組みを形にできる。そうした経験は、個人の成長にも会社の未来にも直結していると思います。
NLPを通じて「自分の業務だけでなく、会社の組織づくりにも関わる」経験を重ねた人が、次の世代を支える存在になっていく。この循環がカルチャーとして今後も根づいていくことが理想だと思います。